公開日:2020.08.25 最終更新日:2021.10.11
CASE
- 法律コラム
- 相続・高齢者問題
遺産分割手続の流れ|弁護士が詳しく解説します

【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
遺産分割手続きは、大まかに次のような流れになります。
- 相続人の確認
- 遺言書の確認
- 遺産の確認
- 遺産価値の確認
- 分割割合を決める
- 遺産の分け方を決める
- 書面化
今回は、それぞれの手続きについて、弁護士が詳しく解説いたします。

1 相続人の確認
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。もし相続人漏れがあると、せっかくまとまった遺産分割協議も、のちのち無効だとしてひっくり返る事態になります。
「被相続人」とは、相続される人、つまり「亡くなった人」をいいます。
「相続人」とは、相続をする人、つまり「亡くなった人の財産を承継する立場にある人」です。
相続では、預貯金などのプラスの“ 積極財産 ”のほか、借金などのマイナスの“ 消極財産 ”も承継する点に注意が必要です。
相続人は、民法886条以下に定められています。大まかに図示すると、相続人は以下のとおりとなります。
1 配偶者
2 配偶者以外(順位:(1) 子孫 → (2) 祖先 → (3) 兄弟姉妹 ※甥・姪)
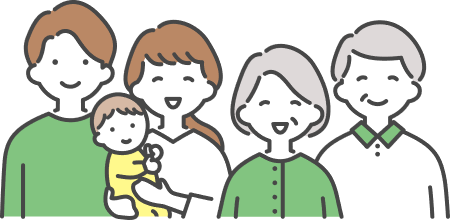
1 配偶者
配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。
2 配偶者以外
(1)直系卑属(子孫)
まずは、子が相続人となります。
子が既に亡くなっている場合には孫が、孫が既に亡くなっている場合にはひ孫が、ひ孫がすでに亡くなっている場合には玄孫が・・・というように、子孫が相続人となります(代襲相続。民法887条2項、3項)。
(2)直系尊属(祖先)
直系卑属に相続されない場合に、相続人となります。
直系卑属に相続されない場合、まずは親が、親が既に亡くなっている場合には祖父母が、祖父母が既に亡くなっている場合には曾祖父母が・・・というように、祖先が相続人となります(民法889条1項1号)
(3)兄弟姉妹
直系卑属や直系尊属に相続されない場合に、相続人となります(民法889条1項2号)。
なお、兄弟姉妹については、その兄弟姉妹の子(甥・姪)までが、代襲相続の対象です。つまり、甥・姪は、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹に相続されない場合、最後に、相続人になります(代襲相続。民法889条2項・887条2項)。
上記の「相続人」以外に、遺産分割に参加する場合はある?
【 被相続人Bの死亡時に、相続人Aが既に亡くなっている場合 】、Aの子が代襲して相続することを「代襲相続」と言い、Aの子が代襲相続人です。一方で、【 被相続人Bの死亡の後に、相続人Aが亡くなった場合 】、「順次相続」と言いますが、“相続人の相続人”という立場で遺産分割に関与することがあります。
| 順次相続のケース 被相続人Bが死亡した後に、相続人Aが死亡しました。相続人Aには、相続人CDEがいます。 この場合、相続人Aを相続したCDEが、順次相続人として、被相続人Bの遺産分割に参加する資格があります。 |
具体例で確認しましょう
1 とある男性には、妻子、父母、祖父母がいました。ある日、父が亡くなりました。
(1)父の相続人は、男性(子孫)と母(配偶者)です。
- もし、父が亡くなる前に男性が死亡していた場合、父の相続人は、子(子孫。代襲相続人)と母(配偶者)です。
- もし、父が亡くなった後に男性が死亡した場合、父の相続人は、男性(子孫)の順次相続人の妻子と母(配偶者)です。
(2)男性が相続放棄をすれば、父の相続人は、祖父母(祖先)と母(配偶者)です。
- 相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。
2 とある男性には、妻子、父母、祖父母に加えて、実は弟(父が生前認知していた腹違いの隠し子)もいました。ある日、父が亡くなりました。
(1)父の相続人は、男性(子孫)、弟(子孫)、母(配偶者)です。
- 弟を抜きにして遺産分割協議をしても、その合意は無効となります。
(2)男性が相続放棄をすれば、父の相続人は、弟(子孫)と母(配偶者)です。
2 遺言書の確認
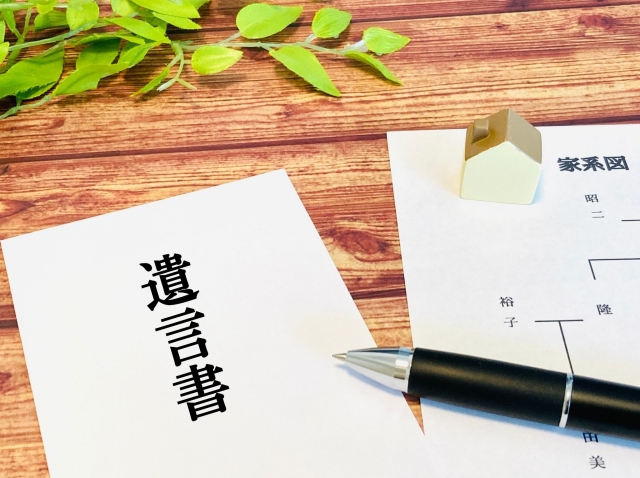
一般用語では「ゆいごん」と呼ばれますが、法律用語では「いごん」と呼ばれます。自分の死後に効力を生じさせるための意思表示です。
遺言を残しておくと、自分の死後は、特段の事情が無い限り、遺言に従って相続財産の分配等が行われます。遺言を残しておくことで、多くの相続争いを未然に防ぐことができ、預貯金通帳の承継や不動産登記等の手続きも楽になります。生前のうちに、遺言を作成しておくことを強くおすすめします。
公正証書遺言とは
公証役場に行き、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらい、保管してもらいます。
方式を誤って遺言が無効となることや、遺言が紛失してしまうことなどを防止できますので、お勧めします。なお、相続人は、最寄りの公証役場にて、全国の公証役場の公正証書遺言保管の有無を確認できます。
自筆証書遺言とは
成年被後見人であるなど判断能力に問題がない限りは、自分単独で遺言を作成することもできます。
ただし、要式行為であり、法律で定められた方式に従っていないときには無効となりますので、注意が必要です。たとえば、日付が書かれていない場合、パソコンで作成した場合などには無効となります。
| 民法968条1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 |
また、複数名でする共同遺言も無効です(民法975条)。一人一遺言(ひとりいちいごん)で作成しなければなりません。
遺言を保管している場合や、遺言を発見した場合はどうすればよい?
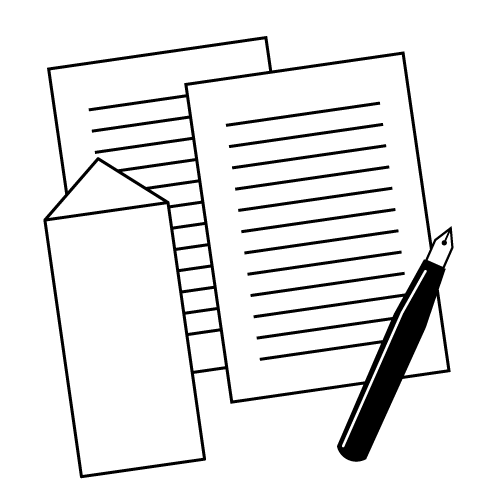
家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません(民法1004条)。
検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせて確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。なお、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、開封しないよう注意が必要です。
なお、日本社会の高齢化及び自筆証書遺言が問題点の多いものであったことから(紛失、亡失のおそれ、破棄、隠匿、改ざんなどの容易さ、有効性等の紛争勃発の可能性を多く孕むものであったことなど)、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が2020年7月に施行されました。
同手続を利用すれば、財産目録のパソコンでの作成も認められ、同法の要式に従い作成し無事法務局に保管してもらった遺言書については検認手続も不要、という制度になっています。
3 遺産の確認
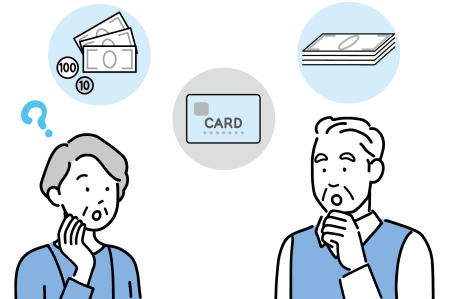
相続人は、相続によって被相続人の権利義務を包括的に承継します。
現金などのプラスの財産(積極財産)も、借金や保証人債務などのマイナスの財産(消極財産)も承継します。
遺産の確認方法
それぞれの遺産の確認方法をみていきましょう。
- 不動産は、名寄せ帳で確認できます。
- 預貯金は、被相続人の所持品調査や、金融機関への問い合わせによって確認します。
- その他、株式、借金等については通知や、動産については現物などで確認します。
なお、生命保険金は、受取人固有の権利であり、遺産分割の対象にはなりません。
また、遺産分割協議においては遺産分割の対象として合意することは可能であっても、裁判所の遺産分割審判手続においては遺産分割の対象とはならないと解されている財産が多く存在することに注意が必要です。
判例上、金銭債権などの可分債権は、被相続人の死亡によって法律上当然に分割されて、各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得します(最高裁最昭和29年4月8日判決等)。この可分債権とは、例えば、貸金、不動産賃料、交通事故による損害賠償請求権などです。
預貯金も、金融機関に対する払戻請求権であり、平成28年12月までは、遺産分割の対象にならないものと解されてきましたが、預貯金の性質から、法律上当然に分割されないもので、遺産分割の対象になるものと解され、判例変更されました(最高裁平成28年12月19日決定)。
仮想通貨は遺産分割の対象となる?
さらには、今後、ビットコインなどの仮想通貨についての相続の問題、遺産分割の対象となるのか否かといった争いも増えそうです。
日本通貨でないため、遺産価値の算定の問題もありますが、その前に保有者死亡後に人知れずとなるケースや、アクセス不能になるケースで、事実上承継されないまま有耶無耶となってしまうといった現実問題も想定できます。
行政で法体制が進んできてはいますが、どのように法整備されるのか等、注目しています。
4 遺産価値の確認

遺産分割協議においては、全相続人で合意できるのであれば、いかなる内容でも原則自由です。しかし、合意ができず、法的に遺産価値を確認する場合は、以下に述べるとおりとなります。
遺産分割協議の際の参考までに、把握しておかれるのもよいかもしれません。
不動産
不動産の価値は、固定資産税評価額が参考にされます。ただ、固定資産税評価額は、原則3年毎に見直しされる価額であり、また、実際の取引価額の70%程度とされ、必ずしも取引価額と一致しないことが多いです。固定資産税評価額ではなく、取引価格、取引相場や時価などによるべきだとする場合には、不動産鑑定を依頼し、複数業者から鑑定書を出してもらいます。
評価基準時がいつであるかという問題については、「死亡時」と「遺産分割時」とが考えられます。例えば、【 死亡時には1500万円だった不動産が、価値の変動によって、遺産分割時には1000万円となっている 】というケースでは、どちらの価値が前提となるのか、という問題です。
これは、どのような目的で評価するのかで異なり、「相続人間の分割割合」を決める目的での不動産評価については、死亡時を基準とすることも多いですが、実際に「遺産の分け方」を決める目的での不動産評価については、遺産分割時を基準とするのが原則です。
実際に遺産を分ける際に、価値の変動を無視して相続開始時に遡って遺産評価すると、相続人間に不公平な結果をもたらす可能性が高いからです。なお、相続税の算定においては、死亡時の価額が前提とされます。

動産
高価な動産についての価値を確認する場合、見積もり書や鑑定書を出してもらいます。なお、自動車も動産です。
現金
死亡時・遺産分割時の金額を確認します。
預貯金
死亡時・遺産分割時の預金通帳残高、金融機関の残高証明書上の残高等を確認します。
株式
「上場株式」の場合は、取引相場において公表されている取引価格によって評価します。
「非上場株式」の価値など、なかなか価値が計算しづらいものの算定については、争いとなるケースが多いですが、相続税申告書記載の評価額が参考にされます。
貸金、賃貸料などの債権
法的には当然に分割される可分債権で、遺産分割審判の対象とはなりません。
遺産分割協議において話し合う場合は、回収可能性の高い債権であれば問題なく額面通り評価してよいですが、回収可能性の低い債権であれば、額面以下の価値しかないものとみなした方がよいことがあります。
5 分割割合を決める

相続分(分割割合)については、「遺言」で定めることもできますし、また、「遺産分割協議」においては、全相続人で合意できるのであればいかなる内容でも原則自由です。
しかし、遺言での指定がなかったり、協議による合意ができなかったりして、法的に分割割合を確認する場合は、以下のとおりとなります。
法定相続分
法で定められた原則的な分割割合(法定相続分)は、次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 | 法定相続分 |
| 配偶者と子(子孫) | 配偶者 1/2 |
子ら 1/2 |
| 配偶者と直系尊属(祖先) | 配偶者 2/3 |
直系尊属ら 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 |
兄弟姉妹ら 1/4 |
| 配偶者がいないとき | 相続人の数に応じて原則均等割合 | |
具体的相続分
上記の原則的な分割割合が「寄与分」、「特別受益」などといった考え方によって修正される事があります。
令和元年7月1日に施行された改正相続法において、親族以外の者(例えば、高齢者夫婦と同居している長男の妻)の貢献についても、金銭的に評価して分け与える「特別寄与料」という新制度も施行されました。さらに、令和2年4月1日から、「配偶者居住権」の新制度も施行されています。
6 遺産の分け方を決める
相続人がそれぞれ取得を希望する財産を確認します。
その財産の分け方(現物分割、代償分割、換価分割)を決め、分割割合に応じて取得できる相続金額と、実際に取得する財産金額との差額について、金銭(代償金)にて調整します。
7 書面化

話し合いで合意できる場合
遺産分割協議においては、全相続人で合意できるのであれば、いかなる内容でも原則自由です。
遺産分割協議がまとまれば、「遺産分割協議書」という書面にします(遺産に不動産がある場合などには特に)。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
話し合いで合意できない場合
話し合いによる合意が整わなければ、調停手続、審判手続という、裁判所を介した手続を利用した書面化(調停調書、審判調書)を考えなければなりません。
遺言書がある場合
そもそも遺言書があれば、相続人において、1~7(相続人の確認~書面化)の手続がほぼ省略可能で、実質2(遺言書の確認)だけで済むことになります。遺言書は、法改正によって昔より利用しやすくなってきており、遺言書の活用を強くおすすめしています。
相続問題・遺産分割のご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ
当事務所は、相続のご相談について、無料相談(初回30分)を承っております。遺産分割手続きについて、ご不明な点等がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
| 「医療・介護」「飲食・ホテル」「小売・店舗」「保育園」「タクシー」「士業」「不動産」「コンサルタント」「人材サービス」「フィットネス」など30名以下のサービス業に特化した顧問弁護士サービス 月額11,000円でお試し可能!詳しくはこちらをご覧ください > |
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
