公開日:2022.04.14
CASE
- 労働問題(企業側)
- 法律コラム
- 労働問題(労働者側)
成人年齢18歳に|企業の対応は?|顧客契約・雇用契約についても解説

【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
民法の改正で2022年4月、成人の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳から親の同意なしで、携帯購入やアパートの賃貸借契約などができるようになります。アルバイトなどを採用する場合も、18歳から親の同意なしでよいのでしょうか。成人年齢引き下げに伴って企業がとるべき対応について、企業法務に精通する福岡・佐賀の弁護士法人 桑原法律事務所の弁護士が解説します。
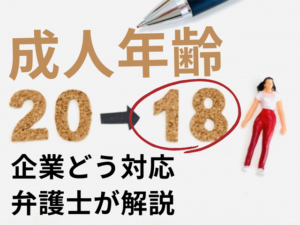
「18歳成人」できること:契約行為
18歳から1人でできるようになった経済的な行為として、下記のような例があります。
- 携帯電話を買う
- アパートを借りる
- クレジットカードをつくる
- ローンを組む
- 証券口座の開設
- 生命保険・損害保険の加入
18歳、19歳の成人に対しては、親の同意がない未成年者の契約を原則取り消すことができる「未成年者取消権」は行使できなくなりました。
このため、消費者としての被害が増えないか懸念されています(後述します)。
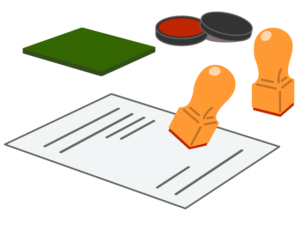
「18歳成人」できること:ステータス・資格
18歳からできることは、下記なども加わります。
- 10年パスポートの取得
- 国籍の選択(2つ国籍のある人)や帰化
- 公認会計士・司法書士・行政書士などの資格取得
- 裁判員への選出
- 性別の変更の申し立て(性同一性障害の人)
「18歳成人」できないこと:飲酒・喫煙など
これまでどおり、20歳からでなければ認められないのは、下記などです。
- 飲酒・喫煙
- 競輪・競馬・競艇・オートレース(公営ギャンブル)の投票券購入
- 大型・中型免許の取得
- 国民年金への加入
Q1. 18歳のアルバイトに「親の同意書」は不要ですか?
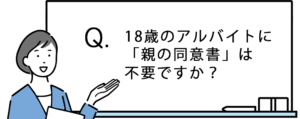
A1. 2022年4月1日以降は、不要となりました。
民法では、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と記載されています(第5条)。
この「未成年者」について、2022年4月から、満18歳をもって成年とするとの改正法が施行されたので(第4条)、18歳以上の者を雇用する場合には、保護者の同意が不要となった訳です。
なお、労働基準法58条を誤解して、15歳以上の未成年者を雇う場合には「保護者の同意」が不要といった解説がなされている記事などもあるようですが、これは民法4条の保護者の同意権と、労働基準法58条の年少者保護の規定の意味を、誤解して執筆されているようですので、注意が必要です。
18歳の成人に対して、法律上は「親の同意」が不要となったとはいえ、当面は、高校3年生のアルバイト採用などにおいて「親の同意」を求める企業も多いでしょう。
「18歳成人」雇用の注意点:ていねいな説明を
18歳から成人とはいえ、社会経験の乏しさは変わりません。これまで以上に、十分な配慮が必要です。

雇用する側には、労働条件を記した通知書の交付が義務づけられています。書面にして渡すだけでなく、ていねいに説明しましょう。
下記のようなトラブル例がありますので、注意しましょう。
- 時給が低い:研修中でも各都道府県の最低賃金以上を支払いましょう。
- 休憩時間がない:法律で義務付けられている休憩時間を確保しましょう。
- 残業代が支払われない:契約で定めた労働時間を超えたら残業代を支払いましょう。
- 突然、辞めさせられた:非正規雇用でも、一方的な解雇はできません。
求人票に「学業を優先」「テスト期間は配慮する」といった記載をすれば、人材も集まりやすくなるでしょう。
Q2.繁忙期だけ学生に「業務委託」として手伝ってもらいたい。注意点は?
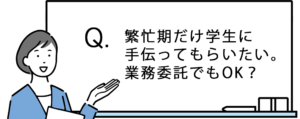
A2. 「労働者」との線引きを明確にし、しっかり説明しましょう。
18歳、19歳は親の同意がなくても「委任契約」「請負契約」といった契約を結べるようになりました。
単発の仕事などを発注する上記の契約の場合、企業と雇用関係にありません。「労働者」には当たらないため、社会保険への加入や最低賃金の適用は原則、必要ありません。
「労働者」とみなされかねない条件を契約で定めると、社会保険や最低賃金の適用を逃れるための契約と判断され、トラブルのもとになります。
下記の項目にチェックが多いと、「労働者」と判断される可能性が高くなります。
- 仕事の依頼や業務の指示に応じる・応じないの自由がない
- 業務の進め方を細かく指示・命令している
- 仕事の時間や場所を拘束している
- 第三者の業務代行を認めていない
- 報酬が時間給や日給
- 他の業者のために働くことを許していない
- 本人の所有する機械・器具の使用を認めない
Q3.18歳・19歳の「成人」顧客への企業の対策は?

A. 約款やサービス利用規約に「未成年者は20歳未満」といった定義づけがあれば、改定する必要があります。保護者の同意を求める定めがあれば、見直すかどうか検討しましょう。契約の流れも確認しましょう。
また、前述の通り、飲酒や喫煙は20歳のままですので、18歳・19歳の顧客へは提供できません。
消費者庁は「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーンとして、対策に力を入れています。
若年者を取引の相手とする事業者に対しても、適切な対応を求めています。とりわけ貸金業やクレジットカードの業界団体に、自主ガイドラインの策定や啓発などに取り組むよう促しています。
国民生活センターでは、18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブルとして、下記を挙げています。
- もうけ話:副業・情報商材やマルチ商法など
- 美容関連:エステや美容医療など
- 定期購入:健康食品や化粧品など
- SNSきっかけ:誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など
- 出会い系:出会い系サイトやマッチングアプリ
- 異性・恋愛関連:デート商法など
- 仕事関連:就活商法やオーディション商法など
- 新生活関連:賃貸住宅や電力の契約など
- 借金・クレカ:消費者金融からの借り入れやクレジットカードなど
- 通信契約:スマホやネット回線など
18歳や19歳との取引でトラブルがあれば、「成人年齢の引き下げにつけこんだ」とみなされかねず、世間の目も厳しいでしょう。
契約や約款の見直しについてお悩みがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
