公開日:2020.09.04 最終更新日:2022.06.15
CASE
- 法律コラム
- 企業法務
任務懈怠責任とは?株式会社の取締役は会社に対してどのような責任を負うか?

【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。
目次CONTENTS
取締役が負う責任は、会社に対する責任と第三者に対する責任の2つに分類されます。
取締役の会社に対する責任には、以下の3つの項目があります。このうち今回は、1「任務懈怠責任」と2.「利益相反取引による責任」について解説いたします。
- 任務懈怠責任(会社法423条1項)
- 利益相反取引による責任(356条1項)
- その他の責任(利益供与の責任(120条4項)・剰余金の配当等に関する責任(426条1項)・出資の履行の瑕疵に関する責任(213条1項))
関連記事:株式会社の取締役は第三者に対してどのような責任を負うか?
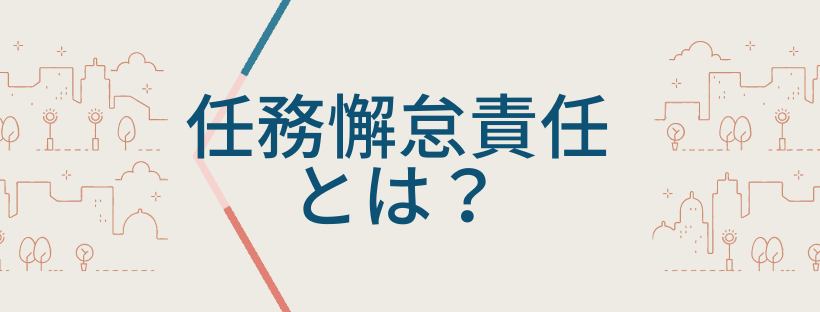
任務懈怠責任とは?
取締役は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(423条1項)。
したがって、取締役の行為によって会社に損害が発生した場合には、当該取締役は会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
では、「その任務を怠ったとき」とはどのような場合をいうのでしょうか。
A 業務執行の場合
まず、取締役の業務執行が任務懈怠とされる場合として、法令違反行為が挙げられます。法令違反は、原則として任務懈怠とされているため、業務を行うに際しては、関連法令の細部まで注意を払う必要があるでしょう。
では、取締役の行為の結果、会社に損害が生じた場合に、ただちに任務懈怠になるのかというとそうではありません。取締役の経営判断の結果、会社に損害が生じても、事後的に任務懈怠とするべきではないという考え方として「経営判断原則」があります。これは、取締役の業務執行時における事実認識や判断の過程に誤りがあるか否かという視点から判断されます。
経営判断原則については、下記で詳述いたします。
B 監視・監督の場合
取締役は、他の取締役の業務執行を監視・監督する義務を負っています。監視・監督義務違反については、当該取締役が、とるべき監視・監督行為をとらなかったか否か(不作為)が問題となります
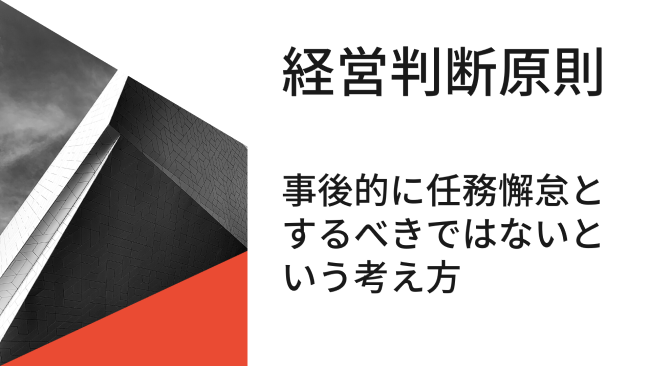
経営判断原則:事後的に任務懈怠とするべきではないという考え方
取締役の経営判断によって会社に損害が生じた場合に、取締役が会社に対して損害賠償責任を常に負うとすることは、取締役の経営に関する裁量を制限することになり、会社の利益にならないと考えられます。
このような原則を「経営判断原則」と言います。
「取締役は、企業経営(業務執行)に係る決定をするに当たり会社を取り巻く社会・経済環境に関する将来の変化を正確に予測することはできない。また、企業経営には冒険とそれに伴う危険が付きまとうものであり、取締役が委縮することなく業務を執行するためには取締役の職務執行に際して広範な裁量の余地が認められなければならない」
(引用:神崎克郎「経営判断の原則」森本滋ほか編・企業の健全性確保と取締役の責任〔有斐閣、1997〕194頁)
経営判断原則に関する裁判例(東京地判平成16年9月28日)
判例上も、経営判断原則は採用されています。例えば、東京地判平成16年9月28日は、次のように判示しています。
「取締役の業務についての善管注意義務違反・・・の有無の判断にあたっては、取締役によって当該行為がなされた当時における会社の状況及び会社を取り巻く社会、経済、文化等の情勢の下において、当該会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験を基準として、前提としての事実の認識に不注意な誤りがなかったか否か及びその事実に基づく行為の選択決定に不合理がなかったか否かという観点から、当該行為をすることが著しく不合理と評価されるか否かによるべきである」
東京地判平成16年9月28日(判時1886号111頁)
経営判断原則は上記判例にも現れているように、
- 情報の収集、分析、検討が合理的であった
- その事実認識を前提にして行った判断が明らかに不合理、著しく不当ではない
という場合は、取締役の判断は「任務を怠ったとき」にあたらず、取締役は損害賠償責任を負わないことになります。
取締役の利益相反取引|取締役会の承認決議が必要?
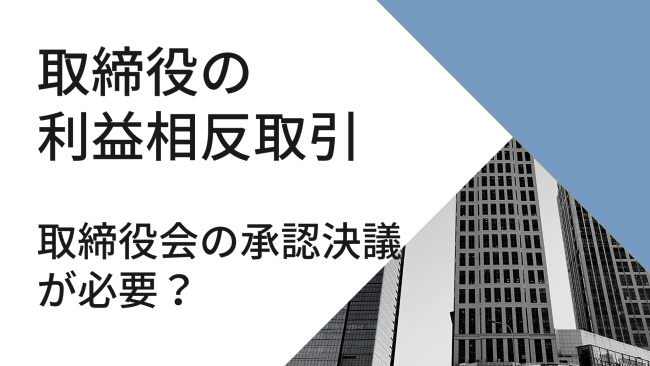
取締役が利益相反取引を行う場合は、原則、取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受ける必要があります。
また、当該取引により会社に損害が生じた場合、任務懈怠のある取締役は、損害賠償責任を負う可能性があります。
1.利益相反取引:直接取引と間接取引
利益相反取引には、直接取引と間接取引があります。
- 直接取引は、取締役が当事者として、または他人の代理人・代表者として、会社とする取引です(会社法356条1項2号)。
- 間接取引は、会社が取締役の債務を保証する等、取締役以外の者との間で会社・取締役間の利害が相反する取引です(会社法356条1項3号)。
2.利益相反取引は取締役会での承認決議が必要
利益相反取引を行う場合は原則、取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受ける必要があります(会社法365条、同法356条1項柱書)。
例外:取締役会での承認が不要なケース
利益相反取引であっても、会社に損害が生じ得ない取引は承認が不要とされています。例えば、会社が取締役から無利息・無担保の貸付を受ける(最判昭和38年12月6日判決)場合などです。
また、承認は株主の利益保護のために要求されているので、会社とその全株式を有する株主との取引(最判昭和45年8月20日判決)、株主全員の同意がある取締役・会社間の取引(最判昭和49年9月26日判決)も、承認が不要とされています。
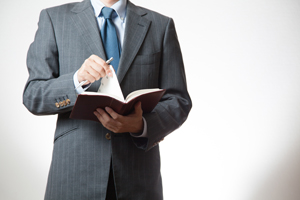
3.承認を受けない取引には無効を主張できる
承認を受けない取引について、会社は、取締役または取締役が代理した直接取引の相手方に対しては、常に取引の無効を主張できます。
もっとも、取引安全の見地から、会社は、直接取引の転得者や間接取引の相手方という第三者との関係においては、当該第三者が、①利益相反取引であること、②承認がないことを知っていることを主張立証しなければ、取引の無効を主張できません。
4.利益相反取引と取締役の損害賠償責任
承認があったとしても、利益相反取引により会社に損害が生じた場合には、その取引に関し任務懈怠のある取締役は、会社に対する損害賠償責任を負う可能性があります。
特に、利益相反取引の当事者となっている取締役だけでなく、当該取引をすることを決定した取締役、承認決議に賛成した取締役は、任務懈怠が推認される(会社法423条3項、同法428条)ので、損害賠償責任を負う可能性が高くなっています。
ご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ
「任務懈怠責任」に限らず、取締役にはさまざまな責任があります。業務執行を行う際に疑問が生じた場合には、そのリスクを専門家に相談し、万全の対策をとる必要があるでしょう。
経営判断原則を前提にしても、「任務を怠ったとき」に該当するかどうかは専門的な判断を要しますので、お困りの際には当事務所までご相談ください。
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。
